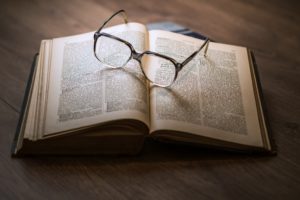ムダを削ぎ落とし、生産性を極限まで高めるためには、何を優先して取り組むべきかを見極める力が必要です。
今回は、和氣忠さんの書籍『イシュー思考』を読みました。
本書では、問題の本質を捉え、「解くべき課題=イシュー」を見極めるための具体的な思考法と手法が紹介されています。
ポイントを整理してみました。
イシューとは何か
イシューとは、単なる問題ではなく、「解けば確実に成果につながる本質的な課題」を指します。全ての課題に取り組むのではなく、本当に意味のある課題に注力することが生産性を高めます。
イシューの見分け方には2つの要件があります。まず「解き得る」ことで、自分やチームの力量で取り組める課題であること。そして「解いた結果のインパクトが大きい」ことです。この2つを満たす課題こそが、本当に価値のある問題です。
本書では、こうした課題に集中することで、無駄な作業や時間を削ぎ落とし、成果を最大化する方法が示されています。
日常業務でも、イシューを意識することで、優先順位の判断が明確になり、結果として効率的かつ効果的に仕事を進められます。
イシューを見極めることは、単なるタスク管理ではなく、本質を捉える思考訓練でもあります。
成果を出すための第一歩は、まず取り組むべき課題を選び抜くことから始まります。
イシューに集中することが、結果として最短で最大の成果を生み出す方法なのです。
イシューアナリシスで課題を分解する
イシューを解くには、まず課題を小さな単位に分解し、体系的に整理する「イシューアナリシス」が有効です。ただ単に網羅的に分解するのではなく、過不足なく、必要な課題だけを取捨選択して分解することが重要です。
分解の過程では、仮説を叩き台として扱い、間違いを恐れず言語化して書き出すことで、頭の中での思考を外部化できます。これにより、課題の全体像と優先順位がより明確になります。
また、結論に至るまでのプロセスを疑問形で整理することで、思考が深まり、脳が活発に働きます。なぜこの課題が重要なのか、どうすれば解決できるのかを自問自答しながら整理することで、解くべき課題が自然と浮かび上がります。
イシューアナリシスは、単なる分解作業ではなく、思考を整理し、優先順位を決め、行動に落とし込むための強力なツールです。
これを習慣化することで、問題解決の効率と精度は格段に上がります。
小さな課題に分解することで、解決可能なアクションに落とし込みやすくなり、成果を着実に積み上げられるようになります。
本質的な課題に集中するための不可欠なステップが、イシューアナリシスなのです。
イシューステートメントで明確にする
イシュー思考では、課題を明確に言語化する「イシューステートメント」の設定が推奨されます。何を解くべきかを明確にすることで、迷いや無駄な議論を避け、効率的に取り組むことが可能になります。
イシューステートメントは、課題の本質を短く簡潔に示し、誰が読んでも同じ理解に至るようにすることが重要です。
ステートメントを作る過程で、再現性のある課題かどうかを確認することもポイントです。つまり、解決策を他者が応用できる形で整理することです。
具体的に言語化することで、チーム内の認識のズレを防ぎ、全員が同じ方向に動けるようになります。
また、課題を明確にすることで、取り組む優先順位が自然と見えてきます。ムダな作業やリソースの浪費を防ぐためにも不可欠な手法です。
最終的には、イシューステートメントを軸にして、思考と行動を一貫させることで、高い成果を効率的に生み出せます。
問題解決を加速させるための基本ツールとして、イシューステートメントの活用は必須です。
本質的な課題に集中することが、成果を最大化する最短の方法である。
Thinking Point